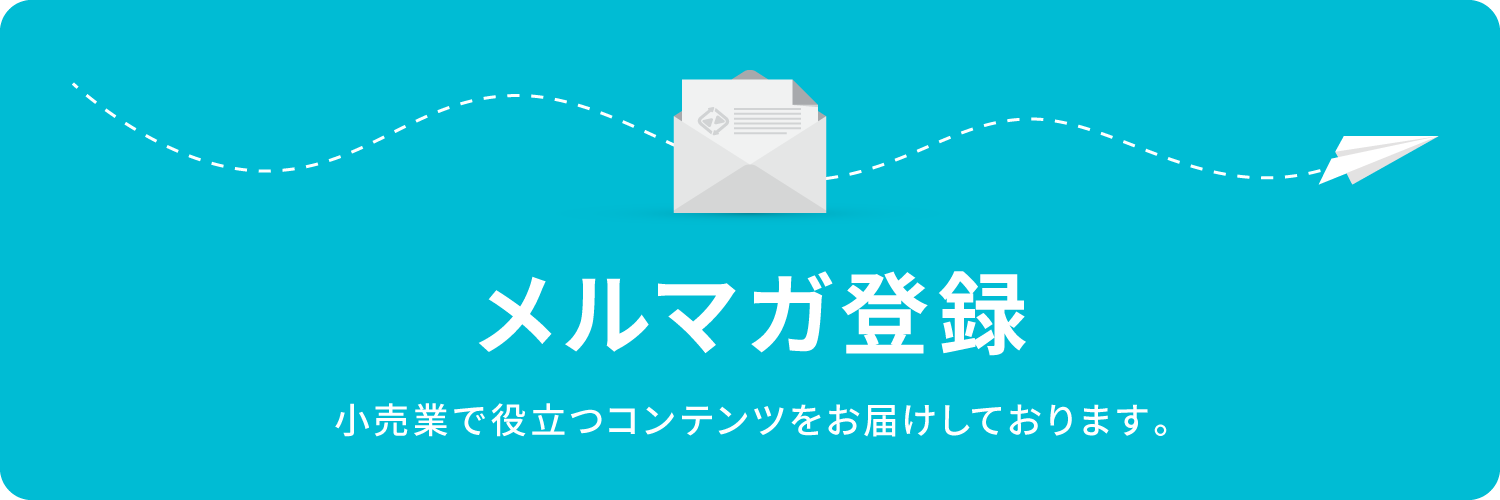2025年の小売業界はどうなる?|3つのキーワードから大予想
2024年も残すところ2週間となりました。小売業界にとっては歴史的な円安による原材料高と物価高、長引く猛暑と経営環境が大きく揺らいだ一年でした。来たる2025年はどのような年になるのでしょうか。昨年に続き独断と偏見でキーワードとともに予想してみたいと思います。
共同配送、越境ECは2025年も続く
筆者はおよそ1年前の2023年11月27日、2024年の小売について予想する記事を公開しました。そこで挙げた3つのキーワードは、外圧(人権デューディリジェンス)、人口動態の不可逆性(物流2024年問題)、グローバリズム(越境EC)でした。
参考:2024年の小売業界はどうなる?|3つのキーワードから大予想
その〈採点〉をしてみます。まず人権デューディリジェンスですが、ファーストリテイリングが原材料の調達までを含むサプライチェーンの管理を始めました。1次取引先(縫製工場)、2次取引先に当たる生地工場、紡績工場(3次取引先)だけでなく、その先にある原材料の調達先まで監査する体制を整えたのです。日本のアパレル企業として初めての取り組みです。
しかし、残念ながらファーストリテイリングに続く日本企業の動きは見られませんでした。人権デューデリは企業にとってコストアップ要因となります。冒頭で触れたとおり、2024年は世界的にインフレが継続し、日本でも実質賃金が上がらない中で物価高が進みました。そうした中で人権デューデリの外圧が強くならなかったとみられます。
ただ、調達先の管理に対する社会的な関心が低くなったわけではありません。労働環境の遵法性や透明性をはじめとした「人権リスク」も同様に低くなったわけではないのです。
それを印象付けたのが、英国BBCによる柳井正ファーストリテイリング会長兼社長のインタビュー放送でした。
柳井氏が「中国・新疆ウイグル自治区の綿花は使っていない」と発言したことが2024年11月28日に報じられたのですが、この発言が中国のSNSで大きな反発を呼びました。競合のH&Mは21年に新疆綿の綿花を使用しないと発表し、同年度の中国での売上高は前年同期から3割弱も減少してしまいました。サプライチェーンと人権リスクの問題は簡単には片付けられない問題のままです。
次に物流2024年問題です。これは、ECプラットフォーマーや物流事業者の間で様々な取り組みが行われています。同じ業界の競合同士が共同配送を実施したり、ECで置き配指定や遅い配送日の指定に対してポイントを優遇するサービスを提供したりしています。
参考:https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/otokushiteibin/
参考:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241007/k10014603101000.html
そして越境ECです。これは、日本企業が積極的に仕掛ける萌芽が見えてきました。典型例が夢展望とTemuの提携です。
インバウンド(訪日外国人)の増加と円安で、海外で日本のアパレルがかつてなく注目を集めています。彼らが日本滞在中に知った商品を帰国後に越境ECで購入するという構図が予想され、2025年も引き続きキーワードとなるのではないでしょうか。
キーワード1:AIエージェントがあなたの分身に
では、2025年のキーワードはどんなものになるでしょうか。筆者は「AIエージェント」「価格競争」「メディア」と考えます。
まずAIエージェントです。2023年後半以降、チャットGPTをはじめとする生成AIが登場し、2024年に入るとまたたく間に多くの業種・業界で導入されていきました。今後は、私たちが能動的にプロンプトを入力して指示せずとも、AIが自ら考えて自律的に動くAIエージェントの開発と実装が本格化していくでしょう。
ソフトバンクが2024年8月にベータ版の提供を開始した「satto」が、AIエージェントについて理解する際の好例になると思います。sattoは、プロンプトを書かずに生成AIを使える手軽さと、さまざまなアプリケーションと連携させられる拡張性、構築したスキル(特定のタスクを実行するパターン)を他人と共有できる汎用性が特長です。
参考:https://www.softbank.jp/corp/news/press/sbkk/2024/20240823_01/
- いつでも、どのアプリを使っていても、AIエージェントを呼び出せる
- GoogleやMicrosoftなどの種々のアプリケーションとシームレスに連携
- ユーザー同士でスキルをやり取りすることで助け合える
こうしたメリットがあることから、AIエージェントを使う人と使わない人とでは仕事の効率や生産性に大きな差が出るのは間違いありません。
また、アクセンチュアは社員と一緒に仕事をこなすAIエージェントを2025年春に全社員に配布します。
参考:https://it.impress.co.jp/articles/-/27190
社員はAIエージェントとコンビを組んでタスクに臨むことになり、社員それぞれの思考回路や癖、特徴を学習したAIエージェントが育つというわけです。AIエージェント同士がコミュニケーションして仕事をこなすことも考えられるとのことで、ここまで来るとまさに「代理人」ですね。
小売は元来、利益率が低く、後述する価格競争の激化や人件費をはじめとしたコスト上昇に伴って利益を上げることがますます難しくなります。AIエージェントの活用による労働生産性の向上が必須となります。
キーワード2:価格競争が進み、業界の新陳代謝加速へ
次のキーワードである価格競争は、2023年、2024年を通じて小売の最重要テーマの1つであり続けました。2025年もそれは変わらず、M&A(企業の合併・買収)や企業倒産をはじめとした業界再編の引き金になるのではないでしょうか。
現在、「103万円の壁」「106万円の壁」をめぐる議論がかまびすしいですが、要は物価が上がる一方で所得(年収)が上がらないなか、いかに手取り収入を増やすかという〈ばらまき〉視点の議論にすぎません。所得が増えないのなら、税や社会保険料といった天引き分を減らすしか手取りを増やす方法はないからです。
つまり、物価高で国民の購買意欲が削がれています。2024年12月6日の日経新聞に掲載された西松屋チェーンの大村浩一社長の「一言」が象徴的です。
お客さまの財布のひもは、まだまだ固い。冬物の価格はできるだけ抑えていきたい。円高・ドル安で仕入れコストが下がれば、還元することも考えないといけない。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO85275600V01C24A2TB1000/
西松屋チェーンは子供服の多くを海外から調達する。2023年から円安を受けて値上げを進めたが、客数も減った。大村浩一社長は「足元では値上げ幅を抑えて客数減に歯止めをかけている」と語る。冬物商戦が本格化するなか気持ちを引き締めていた。
そうしたなか、新型コロナウイルス禍によって売り上げが減少した企業に対して実質無利子・無担保で融資した「ゼロゼロ融資」の返済も2025年には本格化します。政策金融で延命してきた「ゾンビ企業」が倒産で退場し、業界の新陳代謝が進んでいくでしょう。
キーワード3:メディアの役割が重要に
また、小売の観点では、サードパーティークッキーの廃止の流れも見逃せません。広告予算を効率的に使っていくためには、ファーストパーティークッキーを持つことができるメディアとECの融合がますます重要になっていくのではないでしょうか。
サードパーティークッキーの廃止については、2024年6月28日に公開した拙稿「トレンド変化が速すぎるZ世代|「コミュニティ作り」が攻略のカギに」の第1章を参照してください。
広告主となるEC企業にとっての論点は次の2つです。
- サードパーティークッキーの廃止によりターゲティング広告の効果が低下
- CPAが大きく上昇(運用型広告の精度は2割落ちるとの指摘もある)
一方で、広告を載せるサイト側にも影響は甚大です。ネットワーク広告収入が減少するからです。
一部のメディアには既に影響は出ていて、対照的に動画媒体やSNS、検索広告は好調なようです。これらはユーチューブやX(旧Twitter)、インスタグラム、グーグルやヤフーが代表例です。つまり、プラットフォーマーの独り勝ちになるわけです。
とはいえ、ファーストパーティークッキーをもつメディアであればチャンスはまだまだあります。会員情報や顧客データを活用し、メディア訪問者に買い物をしてもらう手法が考えられるでしょう。つまり、メディアとECの垣根があいまいになり、融合していくイメージです。
その1つが、2024年に認知度が大きく上がったリテールメディアと言えます。
参考:LTVと広告効果UPの切り札!?/2024年ビジネス必修語「リテールメディア」の全て」
ファミリーマートのほか、ドン・キホーテを運営するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス、セブン-イレブン・ジャパンが専門部署を新設するなどして広告配信に注力しており、広告精度の向上に余念がありません。小売企業の限られた広告予算や販促予算の〈分捕り合戦〉の様相を呈しています。
まとめ
消費者の価値観はますます多様になっています。そうしたなかでも、低価格であることの価値は比較的普遍なのではないでしょうか。繰り返しになりますが、物価高と実質賃金の低迷により消費者の財布のひもは固く、ECを含む小売企業は生産性向上と広告・販促予算の効率的な投下がますます求められます。AIエージェントやメディアは重要なファクターとなるでしょう。
メルマガ登録受付中!