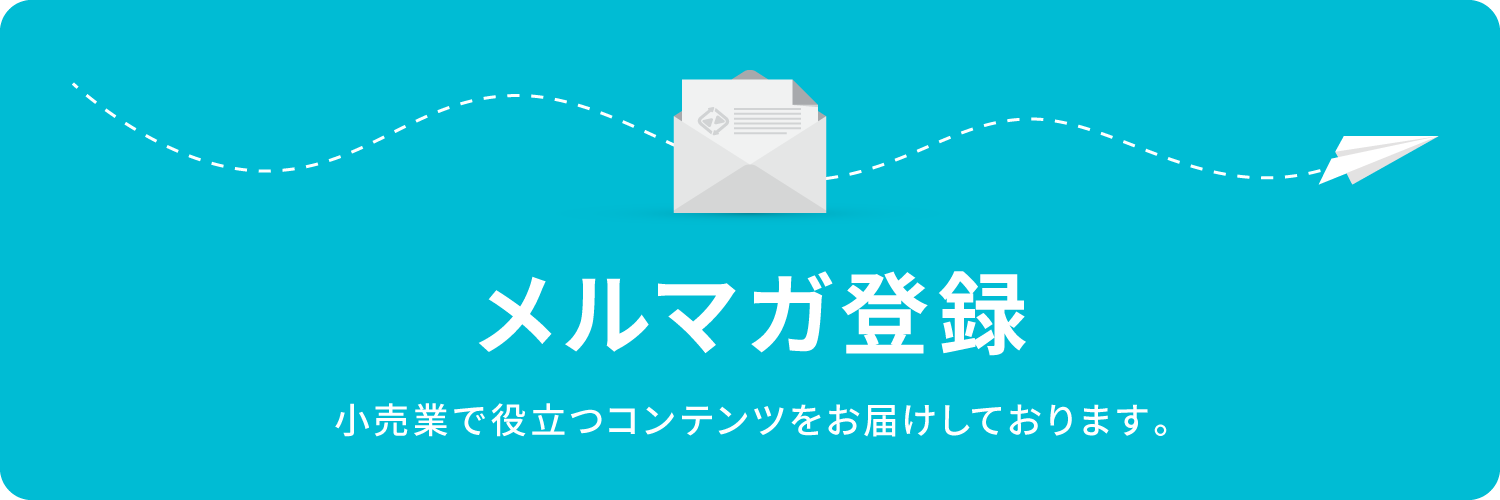ユニクロの強さは「イノベーションを促す仕組み」にあり
「ユニクロ」「ジーユー」などを擁するファーストリテイリングの強さ(収益力、成長力)の源泉は何でしょうか? 創業者である柳井正会長兼社長の強烈なカリスマ性とリーダーシップでしょうか?
正解は「徹底した仕組み化」にあることを、ある書籍が教えてくれました。経済誌の書評で「小売業者の、小売業者による、小売業者のための著作」と絶賛されていましたが、筆者も読んでみて、その評価に違わぬ内容だと感じました。
本記事では、その書籍のエッセンスを紹介します。アパレルをはじめとする全ての小売企業の参考になれば幸いです。
ユニクロの強さとは「将来の成長期待」にあり
その書籍とは、ファーストリテイリング元執行役員の宇佐美潤祐氏による『ユニクロの仕組み化』です。週刊ダイヤモンド2024年12月14日号の書評で「小売業者の、小売業者による、小売業者のための著作」と激賞されていたため、筆者も書店で買い求めて読んでみました。
中身にグイグイと惹きつけられ、一日で一気読みしてしまいました。そして「感想とエッセンスをフルカイテンブログに書き、多くの小売企業の皆さんに届けたい」と思ったのです。

まず、ファーストリテイリングの「強さ」とは何でしょうか。それは売上高成長率であり、利益率であり、財務の健全性(自己資本比率)であり、株価の高さ(時価総額の大きさ)を指すのでしょう。
- 売上高成長率:12.2%(2024年8月期・前期比)
- 営業利益率:16.1%(2024年8月期)
- 自己資本比率:57.7%(2024年8月末)
- 株式時価総額:16.8兆円(2024年12月24日現在)
連結売上高が3兆円を超える巨大企業で2桁の売上増加率はかなり高いと言えます。そして売上高成長率と営業利益率はアパレル企業の中では群を抜いて高く、自己資本比率は申し分ない高さです。その結果が、日本企業6位の株式時価総額に表れています。
宇佐美氏は「企業価値総出力が半端ではない」と述べています*。
(*:宇佐美氏のカギカッコ部分は著書からの引用。以下同様)
その理解のカギはPER(株価収益率)にあります。PERは下記の計算式で求められます。
- PER = 時価総額 ÷ 当期純利益
(株価 ÷ 1株あたり純利益)
つまり、株価が純利益の何倍かを表しているわけです。ファーストリテイリングのPERは43.6倍で、時価総額トップ10企業の中ではリクルートホールディングスに次いで2番目です(2024年12月24日現在)。
PERが高いということは将来における成長期待が高いということです。ただ単に業績(売上高や利益)が良いだけではPERは上がりません。将来も現在と同等以上の利益を上げ続けるという見込みに近い期待があるからこそ、株価が上がるのです。
この要因として宇佐美氏は「イノベーションを促す仕組みと経営スピードを高める仕組みがPERを高める構造になっている」と述べています。まさしく、「仕組み化」がファーストリテイリングの企業価値を創出していて、その結果、優れた商品を次から次へと世に送り出し、世界中の消費者から支持を得ているというわけです。
Whyを明確化した「原理原則」
この章から、その仕組みについて見ていきましょう。まずは「生産性を上げるための仕組み」です。
多くの企業は経営理念を定めているのではないでしょうか。会社によってはミッション、ステートメント、パーパスという呼び名かもしれません。こうした経営理念は非常に重要なものです。バックボーンが異なる多様な人間が会社組織の下に集まり、目指す方向性(ベクトル)を合わせるノーススター(北極星)の役割を果たすからです。
一方で、経営理念は抽象度が高いのも事実であり、宇佐美氏は「経営理念を『自分事化』するための『仕組み』が必要だが、多くの会社ではこの仕組みがない」と指摘しています。それに対し「ファーストリテイリングには経営理念を実践につなげて生産性を高める仕組みがある」というのです。

それが、経営理念と実践との架け橋となる「原理原則」です。言い換えると原理原則は理念とマニュアルとをつなぐものです。宇佐美氏によると、原理原則とマニュアルとの違いは「Why(なぜ)」の有無だそうです。マニュアルにはWhat(何をすべきか)とHow(どう実践するか)は書かれていますが、Why(何故そうするか)は書かれていないからです。
小売の現場では、マニュアルに書かれていない事態が多く発生します。その際、従業員がWhyを理解していなければうまく対応できません。その点、原理原則を理解していれば、それに沿って臨機応変な対応が可能です。
マニュアルを拡大解釈するのでは、案件ごとに企業としての対応にぶれが生じます。これに対し、ファーストリテイリングには「全てはお客様のために」という原理原則が存在します。このため全ての従業員がお客を最優先するという姿勢を貫いて行動できますし、実際そうした行動を起こせるような裁量が現場の隅々まで与えられているのです。
店は客のためにあり、店主とともに滅ぶ
前章でみた「原理原則」の具体例を紹介します。一つは「商品経営の原理原則」です。宇佐美氏によると、ファーストリテイリングが考える最高の商売は「1つの完成された商品だけを大量に売るような商売」とのこと。ユニクロはライフウェアなのでお客はリピーターが中心となりますが、例えば毎年ヒートテックを買っていれば、次の年に買うヒートテックがマイナーチェンジで気に入らなければお客はがっかりしてしまいます。
常にお客の期待を超える商品をつくり続けなければなりません。だからこそ宇佐美氏は「自分たちで自分たちを更新し続ける必要がある」と説いています。
次に「店舗経営の原理原則」です。「店は客のためにあり、店員とともに栄え、店主とともに滅ぶ」という原理原則が柳井氏の社長室に飾られているそうです。
宇佐美氏は、店員が「店は客のためにある」という原理原則から抽象度を下げて自分事化することで、日々のオペレーションの軸ができると述べています。軸があれば、売り手都合ではなくお客を中心にした売り場構成を考えるなど、何をすべきかの判断基準が明確になります。
この辺りは、逆説的です。なぜなら、次のようなジレンマがあるからです。
- お客のために良い最高の商品を提供し続けるには、店舗で儲けを出す必要がある
- 会社の利益第一で売り場をつくると、お客に見透かされる
このジレンマは、売り場のマニュアルに依拠するだけでは解決できません。宇佐美氏は「だからこそお客のための売り場になっているか、どのスタッフでもお客の要望に応えられるのかを常に意識しろ、と原理原則は説いている」と解説します。
これは非常に難しいことですが、ファーストリテイリングでは多くの店舗が実践できているからこそ、好業績を収めることができていると言えます。それはとどのつまり、チェーンストア経営の延長線ではなく、それぞれの店舗が個店経営をするということです。
地域に根差し、地域のことを考えて理解し、柔軟に仕入れを行う姿勢が求められている、と宇佐美氏は強調しています。日本一のチェーンストアであるファーストリテイリングが、実は個店経営の集まりによってグローバル化したという点も大いに逆説的です。
「3倍の法則」でイノベーションを促す
最後に、イノベーションを促す仕組みについて紹介します。これは、店舗スタッフを含む全ての従業員に「経営者目線」によるイノベーションを促すものです。かつ、「チャレンジ」を促す仕組みと表裏一体になっています。
まず、「現在の3倍」というあり得ないほど高い目標を設定します。そんな目標はどう足掻いても無理だ、と思うのも無理はありせません。実際、現状の延長線上の発想では到底不可能です。
だから、ファーストリテイリング社員は、従来からの延長線上の取り組みではなく、新しい発想でチャレンジする方策を必死で考えるのだそうです。
この点、柳井氏は売上高が300億円台の頃は1,000億円を目指し、1,000億円を達成したら次は3,000億円を目指すと公言してきました。宇佐美氏の言葉を借りると、「大ぼらを吹いて、イノベーションを起こすことで有言実行してきた」ということです。
イノベーション数々を挙げてみます。まずは1998年頃に着手したSPA(製造小売業)化です。衣服を仕入れて売るスタイルからの大転換で、今では他の多くの企業がSPA化に舵を切っていますね。
その後、2001年にフリースを大ヒットさせ、中国事業の成長、ジーユー発足、そして2017年の有明プロジェクト(情報製造小売業への進化)と続くのです。
ただ、イノベーションに向けたチャレンジに失敗は付きものです。全ての試みが成功するとは限らないからです。これに対し、ファーストリテイリングには「敗者復活」の仕組みが根付いています。保守的になっている店長に対しては、柳井氏自ら「失敗してもいいからチャレンジしてみないか」と投げかける仕組みがあるそうです。
失敗したとしても、「現状維持よりはマシ」と考える土壌がファーストリテイリングにはあることが分かります。そしてそれは、失敗が明らかになりつつあるときに迅速な方針転換や軌道修正が可能な仕組みと表裏一体です。
また、PDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルは多くの会社で取り入れられていますが、柳井氏がよく「計画1割、実行9割」と説いていることはよく知られています。この点、宇佐美氏はファーストリテイリングではC(評価・チェック)からA(改善)のスピードが速いと解説しています。現場が「原理原則」に従って過去にとらわれず自ら判断し、目的(目標)を達成するための手段を臨機応変に変えていくのです。
こうした即断・即決・即実行の仕組みが、従業員一人ひとりの成長を促し、ひいてはイノベーションを通じた好業績につながるのでしょう。
まとめ
以上は『ユニクロの仕組み化』に書かれているほんの一端です。書ききれない要素もたくさんありました。こうしたさまざまな「仕組み」は、言うのは簡単ですが、構築するのは至難の業です。ファーストリテイリングでは仕組み化を実践できているという事実そのものに柳井氏の凄みが隠れていると感じます。とはいえ、どんな小売企業にとっても仕組み化は必要不可欠です。少しでもファーストリテイリングに近づく努力が必要なのだと思います。
メルマガ登録受付中!